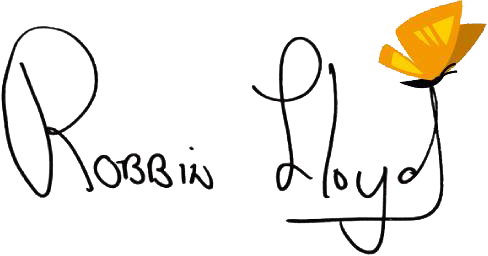日本で「音楽する」外国人–38 文=小沼 純一
民族楽器奏者 ロビン・ロイド
地球を歩き続けて民族音楽を学び
京都にくらすマルチプレーヤー
 古風な家の二階、炬燵にはいっていると、大きな窓をとおして正面に嵐山が見える。折しも初雪が舞い始めたところで、座布団の脇にはみかんという人好きな猫がやってくる。
古風な家の二階、炬燵にはいっていると、大きな窓をとおして正面に嵐山が見える。折しも初雪が舞い始めたところで、座布団の脇にはみかんという人好きな猫がやってくる。
「ここでは、もりあがる激しい曲は作れない。全部おなじになってしまって、これ、ちょっと困ることあるね(笑い)。ときには、東京の人間の動き、あの、なにかうわーっとしたようなのが要る。そうでないと、みんな眠ってしまうような曲ばっかり。尺八吹いたらキマりすぎだし(笑い)」
ロビン・ロイドさんの部屋は、銀閣寺から歩いて1、2分。東京ではもはや見られない懐かしい日本家屋。
「ずっといると日本的になってしまう。だんだんたまってくるものがあるから、時間とお金があれば、旅行に出る。この部屋があればまちがいなくしあわせ。でも生活が狭くなる、そこからちょっとはなれる」
ロイドさんはさまざまな民族楽器を演奏するが、もっとも知られているのは、アフリカの親指ピアノ「カリンバ」。10人前後で始めたワークショップが口コミで広がり、4年間で参加者が2千人を超えた。
「なぜカリンバは流行るかなあと思ったら、これ、ゲームボーイの感覚。炬燵はいって両手の親指でやるんだからね(笑い)」
まずアフリカの地図を広げ、この広大な地域の多様性について語る。そして、ピアノのような西洋近代の平均律とはちがった調律や音階が世界にはたくさんあることを語り、金属片を親指ではじくシンプルなオブジェが立派なひとつの楽器であることを伝え、手ほどきする。参加者はおよそ二時間でひとつの楽器がいじれるようになり、帰りには好みの楽器をおみやげとして持って帰る。
「アフリカの多様性はあまり知られていない。専門家はいるんだけど、大学の先生だったりするから、自分が話をしても意味があるんじゃないかなと。日本にいるから尺八は紹介がやりにくいしね(笑い)」
 ロイドさんはシカゴ郊外の生まれ。子どものときからいろいろ楽器を弾いていたが、高校のときから民族楽器を手に取るようになった。大学ではそれぞれの社会で音楽がどういう位置を占めているかを研究。だが、実際に音楽にさわらないとわからないだろうと思って、海外に出たところ、アメリカには「帰ってこなかった」という。旅の最後の地が京都で、長唄三味線や尺八、琴などを勉強した。女性の師匠さんに習っていたので、京都弁になったが、意識して「途中で捨てちゃった」。
ロイドさんはシカゴ郊外の生まれ。子どものときからいろいろ楽器を弾いていたが、高校のときから民族楽器を手に取るようになった。大学ではそれぞれの社会で音楽がどういう位置を占めているかを研究。だが、実際に音楽にさわらないとわからないだろうと思って、海外に出たところ、アメリカには「帰ってこなかった」という。旅の最後の地が京都で、長唄三味線や尺八、琴などを勉強した。女性の師匠さんに習っていたので、京都弁になったが、意識して「途中で捨てちゃった」。
その後、京都から台湾や中国、アフリカに出掛け、滞在。中国では貴州省の大学で短期間教えたこともあり、その後各地をフィールドワーク。チベットにも足を延ばしている。
日本は、20年以上になる。現在は、演奏活動を中心に、カリンバのワークショップをおこなうほか、専門学校で音楽療法講座も担当する 。
 「アメリカで勉強したひとがやっている療法が多いでしょう。だからクラシックとかいうけど、日本のおばあちゃんのところでベートーベンやってもよろこんでくれない。それよりも、けっして宗教的でないはないけど、シャーマンのようなやりかたができないかと思ってる。カリンバや、アフガニスタンの足につける鈴を使ったり、シンプルに音がでるようなものを使ってね」
「アメリカで勉強したひとがやっている療法が多いでしょう。だからクラシックとかいうけど、日本のおばあちゃんのところでベートーベンやってもよろこんでくれない。それよりも、けっして宗教的でないはないけど、シャーマンのようなやりかたができないかと思ってる。カリンバや、アフガニスタンの足につける鈴を使ったり、シンプルに音がでるようなものを使ってね」
いまは新しいタイプの本を製作中。「音楽ばっかり考えてるのはよくないと思ってる。バランスがわるい。音楽はひとの生活の一部だけ。だから、この本にはいろんなものがはいってる。自分が撮った写真と書いた文章。3曲だけのミニディスク。ハーブティー。指でさわる紙。五感をひらくようなものができたらいいな」
音楽に触れるにも音だけあればいいというものではない。時間と空間、そこにあるほかの要素も大切だ。「おいしい音楽聴いて、まずいハンバーガー食べたらよくないよ。自分が音楽をやるとき、聴いているひとにほかのいろいろなよろこびも感じてほしい。そう思うな」

注)文中に登場する「新しいタイプの本」とは、
2000年に発売されたCD-BOOK『SONgs echo.01』のことです。